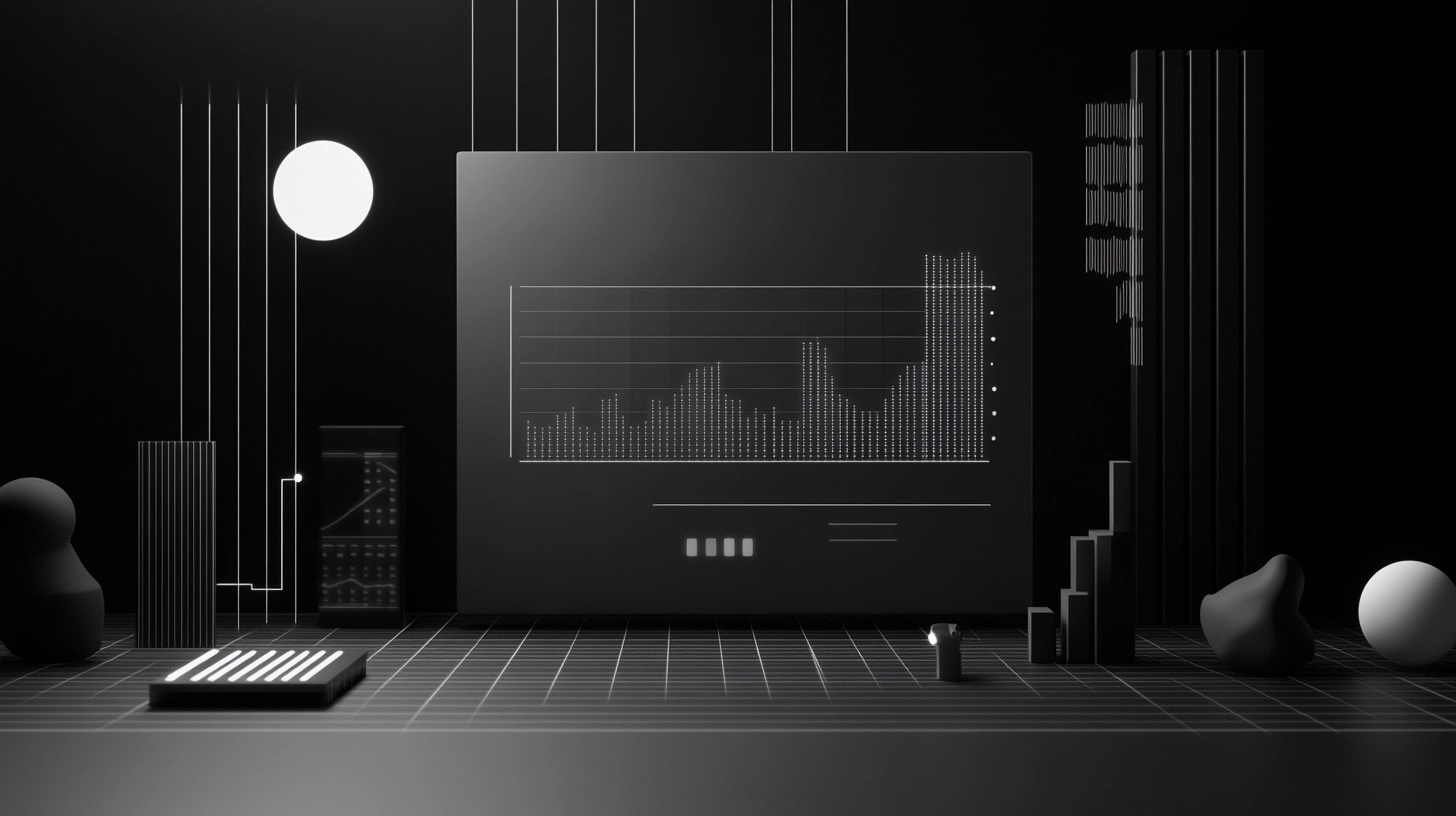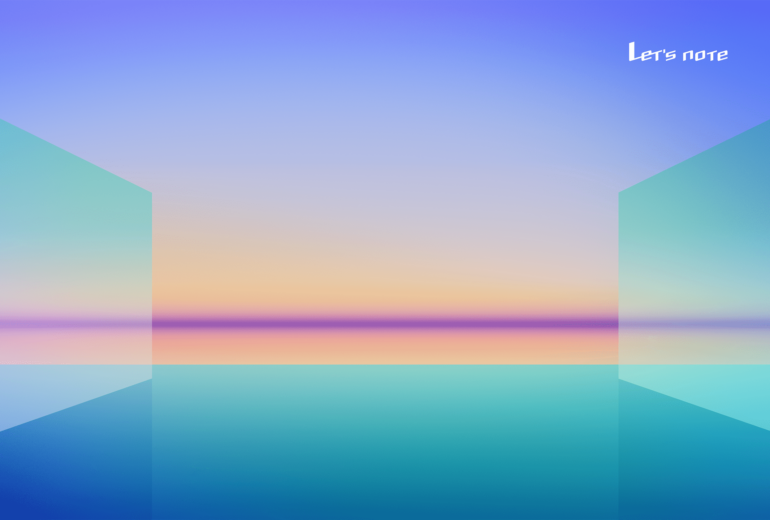「ステマ」という言葉、最近よく耳にしますよね。なんとなく悪いこと、というのは分かるけれど、詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。「ステマ」とは、「ステルスマーケティング」の略称で、消費者に広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する行為のことです。つまり、宣伝だと気づかれないように、あたかも第三者の口コミのように装って宣伝する行為を指します。
ステマにはどんな種類があるの?
ステマには、主に2つの種類があります。
- なりすまし型:
- 事業者自身が、あたかも一般消費者のように装って、SNSや口コミサイトに良い評価を投稿する行為です。
- 利益提供秘匿型:
- インフルエンサーやブロガーなどに報酬を支払い、広告であることを隠して商品やサービスを宣伝してもらう行為です。
なぜステマがいけないの?
ステマは、消費者が正しい判断をするのを妨げる行為です。広告であることを知っていれば、消費者は宣伝内容を割り引いて考えることができます。しかし、あたかも第三者の正直な感想のように見せかけられると、消費者はその情報を鵜呑みにしてしまい、不利益を被る可能性があります。
ステマを見抜くには?
では、私たちはどのようにしてステマを見抜けばよいのでしょうか? いくつかのポイントをご紹介します。
- 極端に良い評価ばかりの口コミは疑う:
- どんな商品やサービスにも、良い点もあれば悪い点もあります。極端に良い評価ばかりの口コミは、鵜呑みにしないようにしましょう。
- 不自然な日本語や表現に注意する:
- 機械的に作成されたような不自然な日本語や、同じような表現が繰り返されている場合は、ステマの可能性があります。
- 情報の発信元を確認する:
- 口コミやレビューを投稿しているアカウントが、信頼できるアカウントかどうかを確認しましょう。フォロワー数や投稿内容などを参考に、総合的に判断することが大切です。
- 複数の情報を比較検討する:
- 一つの情報を鵜呑みにするのではなく、様々な情報を確認して、比較検討をしましょう。
最後に
2023年10月からは、ステマは景品表示法という法律で規制されることになりました。しかし、ステマの手口は巧妙化しており、完全に見抜くことは難しいのが現状です。私たち消費者は、常に情報を批判的に捉え、賢い消費者になることが大切です。